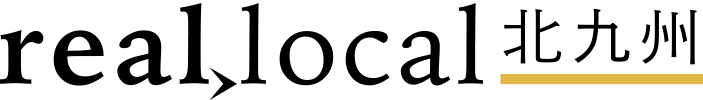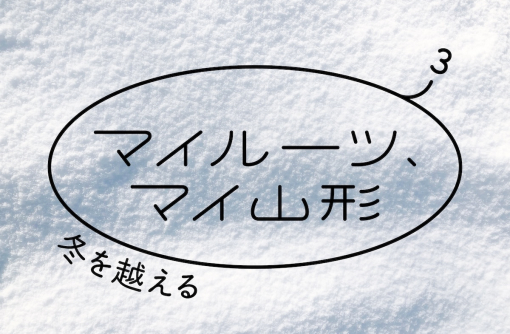【北九州】門司港レトロ30周年!新浜倉庫群から広がる、港の風景。
「よう来ちゃったね〜、ここは初めて?」「あっちから海がきれいに見えるけん、寄ってみて!」 そんなふうに観光客に声をかける地元のおばちゃんや、「シャッター押しましょうか?」と気さくに話しかける高校生。門司港では、そんな小さな交流が日常の中に溶け込んでいます。
レトロな建物が並ぶこの港町は、九州の人気観光地のひとつ。海風に吹かれながらまちを歩けば、歴史の香りとともに、どこか肩の力が抜けるような、やさしい時間が流れていきます。そんな門司港の新たなにぎわいづくりとして、北九州市が取り組んでいるのが「新浜倉庫群アートプロジェクト」。倉庫の壁をアートで彩り、まちに新しい人の流れを生み出そうというものです。
このプロジェクトを通じて、まちづくりに関わる行政の方と地域のプレイヤーに話を伺いました。門司港がこれまで歩んできた時間、そして今、動き始めている新しい風景。少しのぞいてみてください。

混ざりあって生まれる「門司港らしさ」
門司港は、明治初期に開港して以来130年以上の歴史をもつまち。明治から昭和初期にかけて、日本の近代化を支えた国際貿易港として、九州と世界を結ぶ重要な拠点として発展してきました。その港町の情緒を今に受け継ぎながら、観光地「門司港レトロ」としてにぎわいを生み出しているのが、現在の門司港です。
「港があって、山があって、古い建物と新しい建物が入り混じっていて。明治から昭和初期にかけて栄華を誇ったその名残が今も息づいています。でもそこに、今の人の感覚もちゃんと混ざっている。これが門司港の“味”なんです」と話すのは、北九州市 都市ブランド創造局 門司港レトロ課で門司港エリアのまちづくりに携わっている課長の彌榮(みえ)真里さんです。
「門司港は、まちのベースに“この場所を愛している人”がたくさんいると感じています。船、鉄道、海外との玄関口として、この地域は本当に重要な拠点でした。そうした歴史やレガシーが今もまちの空気に残っていて、仕事をしていてもそれを肌で感じます」



明治22年に石炭を扱う国の特別輸出港に指定されて以降、日本の近代化を支えてきた門司港。歴史があるからこそ、その重みがアイデンティティとなる一方で、「新たな取り組みと、、いかに調和させるかが大切」だと、彌榮さんは冷静に見つめます。
「だからこそ、これからはその歴史を大切にしつつ、新しい視点やエッセンスを積極的に取り入れていきたい。門司港レトロもそうですが、北九州市全体のポテンシャルを上げていくために、“関門エリア”全体を見据えた展開を進めていこうとしています」
レトロ地区としての門司港は、1995年にグランドオープンしてから2025年で30周年を迎えます。行政が整備したインフラの上に、地域の人たちがイベントやお店を重ねてきました。北九州市として、今後は関門海峡の“九州最北端”を活かした観光ルートづくりも進行中です。
「この壁、こんなに素敵だったっけ?」
古い建物に新しいアイデアが加わり、レトロとモダンが混ざり合うこの場所に、2025年春、新しい風景が生まれました。
第2弾となる「新浜倉庫群アートプロジェクト」は、倉庫の壁面にアートを施す取り組みで、北九州市が2024年から門司港レトロ地区の新たな観光コンテンツとして進めているもの。舞台となったのは、門司港レトロ地区と和布刈地区の中間にある新浜倉庫群の壁面です。運営したのは、ミューラルプロデュース専門会社・WALL SHARE株式会社。3月22日には、プロのアーティストTITI FREAKさんと、地元の保育園や幼稚園の子どもたちが一緒に絵を描く「ミューラル・キッズワークショップ(共同ペインティング)」が開かれ、全長18メートルの壁に、のびのびとした色と形が描かれました。
プロジェクトに参加した子どもたちは、スプレーの扱いを学びながら自由にペイント。完成した壁画は、子どもたちの無邪気さとプロの技が交わった、カラフルで晴れやかな風景になりました。ミューラルを見て、思わず立ち止まる人も。「ここ、こんなに明るかったっけ? 通り道が明るくなっていいわ」と、地元の方からも声が上がります。






まちの風景をつくるのは、ご近所さんたち
門司港エリアの風景や「新浜倉庫群アートプロジェクト」を支えているのは、行政だけではありません。地域で日常を営む“ご近所さん”の存在があります。
その一人が、新浜倉庫のそばで「ZATTA ZISSE(ザッタジッセ)」を運営する相浦圭太さん。プロジェクトでもアーティストの制作を支えておられました。
「ミューラルは屋外で描くものでしょう? 最初は、アーティストさんが雨宿りする場所がなくて。トイレを貸したり、自転車を貸したり、荷物を預かったり。そんなやりとりをしているうちに、気づけば一枚の壁に作品が完成していましたね」

ザッタジッセは税理士事務所をベースにしながら、フリースクールやマルシェ、映画上映、寄席など、多様な活動が交わる自由なフリースペースです。その背景には、相浦さんがかつて訪れたサンフランシスコでの体験があります。肌の色や宗教も違う人々が、カフェの片隅で自然と交わりながら語り合っていた。そうした“ごちゃ混ぜ”の空間からこそ、面白いものが生まれると感じたそうです。
ルールや契約は設けておらず、最初に一度だけ面談し、ザッタジッセの考え方に共感してもらえれば、あとはチャットで日程を共有。使いたい人同士が顔を合わせて調整しながら、先着順で使うスタイルです。マルシェの隣で親子向け教室を開いたり、音楽を流して食事を楽しんだり。そんな風景が、6年以上かけて自然と育まれてきました。


特別に宣伝しているわけでもなく、利益を出すことが目的でもありません。ルールも決めていません。ただ、訪れた人が少しずつ何かを始めたくなる。そんな空気が、6年以上の時間をかけて、じわじわと育まれています。
きっかけの向こうにある、まちの物語
「相浦さんの話を聞いて、改めて門司港って、人を引き寄せる魅力がある場所なんだなって思いました」と彌榮さんは話します。「特に印象的だったのは、“ルールに縛られない”という考え方。自由な発想で、誰もがチャレンジできる環境をつくる——まさにその実践をされている。それって、大きな支援ですよね」
まちづくりといえば、計画書や整備事業を思い浮かべがち。でも門司港では、“なんとなく始まって、気づけば面白くなってる”ことの方が、実は多いのかもしれません。
「門司港には、何かが生まれやすい空気があります。アーティストやスタートアップを目指す人たちも、きっとこのまちにインスピレーションを受けている。だからこそ、アートプロジェクトもこれからさらに育っていく可能性があると感じています」と彌榮さんは語ります。
「新浜倉庫群アートプロジェクト」は、今後も続いていく予定なのだそう。今後提供される予定の壁の軒数とその写真を見て、相浦さんは鳥肌が立ったと言います。


「ミューラルは、屋外美術館のようなもの。いつか壁画の前に、仮でベンチを置いてみたいですね。コーヒーを飲みながら絵を眺める人がいても楽しそうだなって。そんな日常の風景がイメージできました」と語るユーモアのある相浦さんの言葉。
プロジェクトは、一つのきっかけにすぎません。でもそのきっかけがまちを変えていく一歩になり得ます。門司港が育んできた歴史や文化に、今を生きる人たちの自由な発想や行動が重なることで、また新しい魅力が少しずつ生まれていく……。その積み重ねが、「また来たいな」と思わせるまちの空気をつくっているのかもしれません。