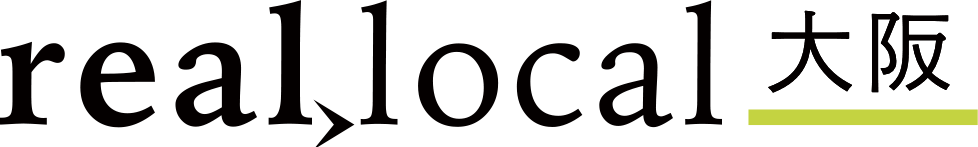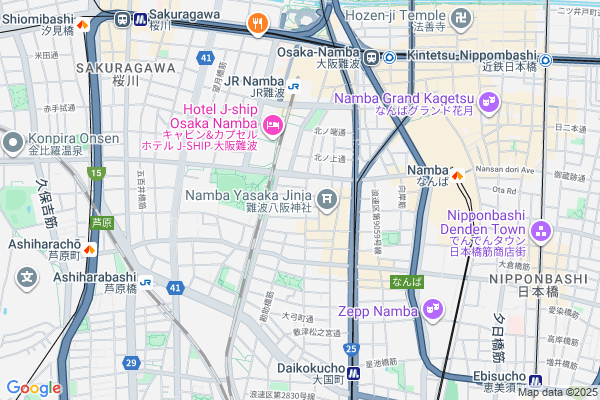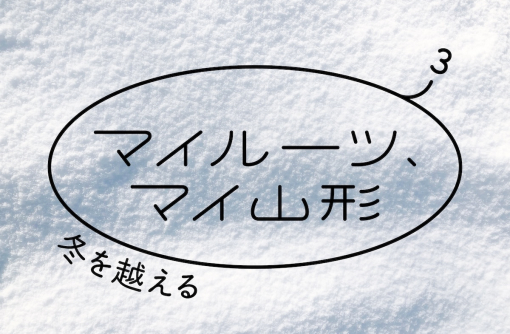繕い、継いでいく|“ミナミの⼟蔵”から広がる⾦継ぎの世界
大阪難波にある金継ぎと器の店「繕継」。店舗兼金継ぎ工房として使われているのは、なんと築年不詳の“土蔵”です。
大阪ミナミの中心部・難波に土蔵があるなんて驚きですが、さらにワンルームマンションのエントランスを抜けた奥にあるという不思議な立地……。誰もこんなところに“土蔵”が存在しているなんて思わないでしょう。
そんな土蔵の中で、日々、金継ぎによって器に新たな命を吹き込む店主兼金継ぎ職人・北尉介さん。金継ぎの魅力とは?そして土蔵ならではのエピソードとは?北さんにお話を伺いました。

「金継ぎ」との出会い
ーー店主であり、金継ぎ職人でもある北さん。初めて金継ぎと出会われたのは、どのようなきっかけだったのでしょうか。
「2011年から日本の陶磁器や料理道具を扱う卸会社の香港支社に勤務していました。日本から香港へ商品を送る際には、どうしても毎回いくつかの器が破損してしまうことがありました。
新品でありながら、物流の過程で壊れたというだけでゴミになってしまうーー
その状況に強く『もったいない』という気持ちを感じていました。
そんなとき、日本独自の修繕技法である金継ぎの存在を知りました。」

心の中に芽生えた「壊れた器を直せる器屋を開く」という目標
ーー金継ぎの存在を知り、深く関わっていく中で、「金継ぎ職人」という道を選ばれた背景には、どんな過程があったのでしょうか。
「最初は金継ぎや漆芸に関する本、インターネット上の情報、動画などを手がかりに独学でスタートしました。トライアンドエラーを繰り返しながら、少しずつ技術を身につけていきました。そのころから『将来、壊れた器を直せる器屋を開きたい』という目標が心の中に芽生えました。
2017年からは香港で金継ぎのワークショップを開催していました。そして2019年に帰国することを決め、翌2020年に日本に戻ってきました。
帰国直後の2020年から2022年は、ちょうどコロナ禍と重なった時期でしたが、この2年間は京都に住み、金継ぎ教室2軒、漆芸教室1軒に通い、再度金継ぎ、漆に対しての知識、技術を学び直しました。」

金継ぎという技法に惹かれただけでなく、日本の文化全体に対する想い
「もともと飲食が好きで、母の影響もあり、幼少期から良い器に触れてきました。そうした体験が自然と器への興味につながっていったのだと思います。
日本は高度経済成長期以降、経済的な恩恵を受ける一方で、本来大切にしてきた文化や風習を少しずつ失いつつあるのではないかと、感じています。
大量生産・大量消費を繰り返した結果、モノは溢れていますが、人々の心の余裕はむしろ失われ、なんだか疲弊しているように思います。『足るを知る・もったいない・侘び寂び』といった精神が、置き去りになりつつあるのではないかと思います。」

ミナミに土蔵? 不思議な物件に感じた“強い縁”
ーー北さんがこの土蔵と出会ったのは、大阪R不動産で賃貸募集の物件を見つけたことがきっかけでした。初めてこの土蔵を見たときは、どんな印象を持たれましたか?
「結婚を機に大阪に引っ越すことになり、もし良い物件があれば、直せる器屋さんをやりたいと考えていました。もともとは、1年くらいかけてゆっくり探せばいいかな、くらいの気持ちでした。
そんな中、最初に今の土蔵の物件を大阪R不動産さんのサイトで見つけました。
私がやりたいことにぴったりの物件でした。外装はある程度修繕されており、内装はほぼ元のまま。趣があり、ぜひ一度内見したいと強く思いました。ご縁だなと感じました。」


*リノベーションの企画・設計施工はアートアンドクラフト。詳細はこちら▷ミナミの土蔵
ーー金継ぎと土蔵とのマッチングは理想的でした。特にもともと設置されていた古家具も、漆の「室(むろ)」として利用されていたことが印象的です。
「漆を扱うには温度や湿度の調整が必要ですが、土蔵は漆を扱うのにとても良い環境です。内見したときには、『ここなら自分がやりたいことができるし、初期投資もそれほどかけずにすぐ商売が始められる』と感じました。
建具もそのまま使用できるとのことで、ほぼ全て置かれていたものを活用させていただいています。必要なものがほぼ揃っており、内装の見積もりもアートアンドクラフトさんにお願いしたらすぐに対応していただけました。最小限の予算で、最短で営業を開始できたのは、大阪R不動産さん(運営はアートアンドクラフト)と大家さんとのご縁のおかげだと、本当にラッキーに思っています。」



海外ゲストにも大好評!ミナミの土蔵から広がる金継ぎの世界
ーーインバウンド訪問者も多い難波。繕継さんを訪れるゲストの方々は、土蔵を実際にご覧になったとき、どのような反応をされますか?
「繕継にも多くの海外の方が金継ぎ体験に訪れてくださいます。難波で土蔵があるのは非常に珍しく、海外の方にも喜んでいただいていますが、日本人の方にも老若男女問わず楽しんでいただいています。年配の方には懐かしさを感じていただき、若い方には新鮮さを感じてもらえるようです。」
「ただ、2階への階段はほぼ梯子に近い角度です(笑)。また2階の天井の高さは海外の方には低く感じられることがあるようですね。壁も経年劣化などで、少し脆い箇所があります。土蔵ならではだなと思います。」



金継ぎはつなぐ文化。土蔵の歴史と重なる「繕い、継いでいく」こと
ーーこの場所と出会い、ご自身のアトリエやお店を構えられたご感想は?
「想定よりも早く、多くの海外のお客さんが金継ぎ体験や器の購入に訪れてくださり、大変嬉しく思っています。
また、現在住んでいる場所から自転車で通える距離であることもあり、人生の中でこの土蔵を借りて商売ができていることを、本当にありがたく感じています。」
日本古来の価値観が食や器、そして暮らしをより「豊か」にしてくれる
ーー今後の展開に向けての想いは?
「家族やパートナー、友人と囲む食卓は、五感を刺激し、とても豊かな時間を過ごせる場だと信じています。その食卓を彩る料理や器は、とても大切な存在です。
日本は世界でもトップレベルの陶芸技術を持ち、実は世界一といっていいほど食器の種類が多い国でもあります。日本には四季があり、四季折々の食材を盛り付けるために、器の存在は欠かせません。
もちろん、大量生産の安価な器も良いのですが、作家さんの器には心を豊かにしてくれる力があります。そして金継ぎがあるからこそ、壊れても直してまた使うことができる。そうした循環が、人の暮らしや心をさらに豊かにしてくれると信じています。
食卓や心、そして日々の暮らしを少しでも豊かにできるよう、お役に立てればと思いながら、日々精進してまいります。」

土蔵で金継ぎ体験、してみませんか?
繕継では金継ぎ教室を随時開催しています。金継ぎに挑戦してみたい方、漆に興味がある方、ぜひお問い合わせください。
貴重な土蔵空間を体験できる機会でもあります。建物にご興味がある方にも、きっと楽しんでいただけると思います。
※繕継では本漆を使用し、金継ぎを行っています。そのため、少し時間も手間もかかり、かぶれのリスクもありますが、飲食に使う器なら天然素材である本漆での金継ぎがお勧めです。
※かぶれについては体質・体調によりさまざまですが、できる限り対策・対応を心がけています。