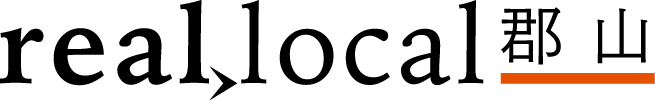かっこ悪いと思ってた家業が遊び場になるまで 「宝来屋本店 」柳沼真行さん
こだわりの糀を使い、味噌やあま酒を製造している「宝来屋本店」。そんな宝来屋で工場長を務める柳沼真行さんはまさに発酵オタク。しかし、取材中にぽろっと口からこぼれた「実は味噌なんてかっこ悪いって思ってたんです」の一言。その言葉の背景にあるストーリーと発酵食文化への想いをじっくり語っていただきました。

1906年、郡山市で創業した「宝来屋本店」※以下宝来屋。味噌やあま酒などに使う糀を販売するお店としてスタートしました。現在は110年以上にわたり蓄積してきた糀づくりの経験と、科学データを活かしてつくった、「総破精(そうはぜ)」と呼ばれる真っ白な糀を使い、味噌やあま酒を製造販売しています。
さらに、海を渡り10カ国以上での販路拡大、地元のコーヒー屋さんやスポーツクラブとのコラボ商品の開発。そのような新たな取り組みを続ける宝来屋は、県内の発酵食品会社の中でも目立つ存在になっています。
特に注目したいのが次々と生み出される新商品。開発の中心にいるのが専務取締役兼工場長の柳沼真行さんです。
取材中、発酵の話題になると話が止まらないほど発酵好きであることが伝わってくる柳沼さん。しかし、話を聞いていると「正直、自分の家の仕事に全く興味がなかったんです。味噌なんてかっこ悪いと思ってました」と驚きの一言。
柳沼さんが発酵食文化に魅了され、宝来屋の歴史を継ぐ1人になるまでのストーリーを伺いました。
家業を継ごうとはぜんぜん思ってなかった

宝来屋の3代目・柳沼正人さんの次男として生まれた柳沼真行さん。物心がついたころには家業との接点はほぼなかったため、あまり馴染みがなかったといいます。
「僕の姉と兄は仕事をしているじいちゃんやおばあちゃんとか親の姿を幼い頃から見てました。だけど、僕は物心ついた頃には自宅兼販売所になっていた家から引っ越していたため、あまり家業に触れる機会がありませんでした。親父は仕事が終わるとスーツで帰ってきてたので、宝来屋でどんな仕事をしてるのかもイメージできなくて。実はすごく好き嫌いが激しかったこともあって味噌汁もあまり好きじゃなかったんです」
これまで家族で仕事を継いできた柳沼さん一家。3代目を担うお父さまは柳沼さんの兄・広呂人さんを跡継ぎにしたいと考え「おまえは将来社長になるんだぞ」といつも言っていました。一方、柳沼さんは「自由にやりたいことをやりなさい」と言われ育ったといいます。
「正直、自分の家の仕事が嫌いだったんです。『お前も継がないか?』と何度か言われたこともありましたけど、味噌なんてダセェ、そんなのやんねぇよって言い返してました。当時は家業を継ごうなんてぜんぜん考えてませんでしたね」

家業との関係がますます離れ、中学生になった柳沼さんが徐々に興味を持ち始めたのは海外の音楽や映画でした。毎月発売される映画雑誌は欠かさず買い、受験勉強の合間もずっと洋画を見るほど海外の文化にのめり込んでいった柳沼さん。その頃から「海外で働きたい、海外と取引のある会社で働きたい」という夢が芽生え始めます。
高校、大学では合計1年2ヶ月のカナダへの留学を経験。大学卒業後は夢だった海外と取引のある東京の会社に入社します。営業担当として忙しくも充実した日々を過ごしていた柳沼さんでしたが、ストレスフルな東京での生活に少しづつ嫌気がさし、福島へ帰ることを考え始めました。入社2年が経ったある日、お父さまから電話でこんなことを言われます。
「兄貴も東京から戻ってきて仕事を継いだし、おまえも郡山に戻ってくるつもりはないか?」
東京を離れたいという思いが高まっていた時期とお父さまからの電話のタイミングが偶然にも重なります。ダサいと思っていた家業を継ぐのに葛藤はあったものの、奥さんと子どもを連れ郡山に戻ることを決断。当時のことを柳沼さんはこう振り返ります。
「よっぽど東京の荒波にもまれて疲れてたんでしょうね。親父が言っていることをあまり理解せずに郡山に戻ると決断しました。あと、田舎の空気がきれいなところで子どもを育てたいと思い始めていたのも、すぐに決断した理由でしたね」
『もやしもん』を読んで思った。発酵の世界おもしろいじゃん!

宝来屋に入社当時、26歳だった柳沼さんがさっそく配属されたのは糀づくりなどを工場で行う生産部。東京でのスーツを着て働くスタイルとは違い、工場内では白衣にマスク。糀が何なのかも分からずはじまった宝来屋での仕事は、東京の仕事とはまた違った大変さがありました
工場の中は機械の音が鳴り響き、仕事を教えてくれる先輩の声はただでさえ聞きとりづらい状況。さらに聞き取るのを難しくさせていたのが、先輩社員の東北なまり、そしてマスクでした。
「工場内ではそんな状況だから、教えてもらっても全然聞き取れませんでした。「もう一回教えて下さい」と言って教えてもらっても、聞き取れないから途中からうんざりしてきちゃって。いまは慣れましたけど、当時は東北なまりが嫌いになってましたね(笑)」
自ら「僕、ビッグマウスなんです」と笑いながら話す柳沼さん。一人じゃできないような仕事も一人でできると言い、味噌樽をひっくり返してしまったり、糀をホースの中につまらせてしまったり。
そんな数々の失敗を繰り返すなかで「悔しい…でも、社長の息子として特別扱いもされたくない」。そんな葛藤を抱えながらの慣れない仕事は精神的にも肉体的にも負担がかかっていたのでしょう。入社わずか1ヶ月で柳沼さんは8kgも痩せてしまいます。

そんな日々が続き、挫けそうになっていた柳沼さんの心にそっと火を付けてくれたのはお父さまが見せてくれた『もやしもん』(講談社)というマンガでした。
「『もやしもん』は農大に通う男の子のストーリーで、その子は菌が見えるっていう設定なんです。はじめは、なんじゃその設定は!?って感じだったんですけど、読み進めると発酵にまつわる菌の話が可愛らしいキャラクターですごくわかりやすく書いてあって、『発酵って面白いじゃん!』と思い始めたんです」
思っていた以上に頭も体も使う仕事に苦労するなか、お父さまから渡された一冊のマンガ。そのマンガを読んだことを機に柳沼さんは発酵の世界にのめり込んでいきます。

劣等感が意外な形で強みに
徐々に発酵の知識を身につけていった柳沼さんですが、発酵食品業界の人と関わるなかで、ある劣等感を感じるようになります。
「発酵食品業界の人の集まりに行くと「どこの農大ですか?」って絶対聞かれるし、ほとんどの人が農大か農学部出身なんです。そんななか、僕は実家が糀屋さんだけど、継ぐ気がなかったから一切発酵のことは勉強してきてない。そのことに劣等感を感じてました」
同じ場所で学んでいるだけではダメだと判断した柳沼さんは、外部で学ぶ機会を求め麹研究会に所属。研究会のメンバーと全国の酒蔵や味噌工場に足を運びます。全国各地で見たことや聞いたことが「もやしもん」の世界と重なり、「発酵について知りたい」という学びの意欲がさらに増していきました。

柳沼さんが力を入れたのは現場での学びだけではありません。味噌ソムリエや発酵食品ソムリエ、国家資格である味噌製造技能士1級の資格も仕事の合間をぬって取得。ここまで自分を突き動かした原動力は発酵への興味もありましたが、劣等感からうまれた「ハングリー精神」だったと柳沼さんは当時を振り返ります。
一方で、発酵を学問として学んでいないという柳沼さんのバックグラウンドは、いま、意外な形で活かされています。
「大学だから学べることはもちろんあると思います。でも、僕は発酵をアカデミックに学んでないからこそ、味噌はこうなんだ、あま酒はこうなんだっていうつくり手のエゴに縛られず、面白いと思ったものを自由につくることができているんです」
看板商品であるあま酒を例にとると、これまでに販売したものだけで18種類。いかに自由な発想で宝来屋が柳沼さんを中心に新商品の開発をしてきたかがわかります。
「あま酒の味のアイディアはデパ地下の菓子コーナーからもらうことが多いです。『この味、あま酒にあったら面白いかも』と思ったらメモしておいて、月に一度やっている新商品開発会議で共有してます。東京への出張のときは必ずデパートに行って、1,2時間はついつい見て回ってしまいますね。もう職業病です(笑)」

発酵食文化に対する固定概念を覆すのが兄と僕の代の使命
一本の電話と一冊のマンガがきっかけで家業を継ぎ、発酵食文化にのめり込んでいった柳沼さん。そんな柳沼さんにとって宝来屋とは、発酵食文化とはどんな存在なんだろう。気になって聞いてみると、「マラソンと同じような感じです」と意外な答えが返ってきました。
「食べ物を長持ちさせるために生まれた発酵食文化は化学や歴史など、さまざまな要素が絡み合い、奥が深すぎて学んでも学んでもきりがありません。学ぶ大変さはありますが、知る楽しさは無限大です。趣味でやっているマラソンのように、発酵食文化について学ぶのも僕にとっては楽しみのひとつなんです。だから、僕にとって宝来屋は遊び場のような存在とも言えますね。
仕事をしていて嫌なことがあると、他の仕事やろうかな〜と一瞬頭をよぎることもあるけど、いまの仕事よりやりたい仕事が思いつかないんです。味噌なんてダセェって言ってたのに、これだけ発酵にハマってるのも不思議ですよね(笑)」

若い世代の味噌汁離れもあり、味噌業界は右肩下がりなのが現状。1,300年以上の歴史がある味噌文化も、つくり手が工夫していかなければ途絶えてしまうと柳沼さんは危惧しています。
「味噌とかあま酒ってオシャレなイメージはないですよね。これって若い世代の発酵食品に対する正直な思いだと思うんですよ。僕が宝来屋を継ぐまで抱いていた『発酵食品=ダサい』というイメージと一緒です。でも、僕がそう思っていたのは発酵食文化をよく知らなかったから。『もやしもん』を読んだり、全国の発酵文化に携わる人の話を聞いたりすることで発酵って面白いって思えた。固定概念を覆すのには何かしらのきっかけが必要なんです。
だからこそ僕たちはSNSで積極的に発信をしたり、福島のスポーツクラブとのコラボ商品を発売したり、若い世代が発酵食文化に触れるきっかけづくりを積極的にしています。歴史ある発酵食文化のバトンを次の世代につないでいくために、発酵食品に対する固定概念を払拭する。それが兄と僕の代の使命です」
取材を終えて
取材後、一緒に話を聞いていた取材班の一人が「死ぬ前に食べたいものは何ですか?」と聞くと、柳沼さんはう〜んとしばらく考えてから教えてくれました。
「ごはん、納豆、キムチ、味噌汁かな」
味噌汁が嫌いで、味噌なんてダサいと思っていた当時の柳沼さんからはきっと返ってこなかった答えですが、発酵食文化に魅了され宝来屋の歴史を継ぐ1人になったいま、その答えは少しの違和感もなく自然に聞こえました。
宝来屋での仕事も発酵について学ぶのも趣味の延長だと楽しそうに語る柳沼さんをみていると、もうすでに、発酵食文化のバトンは周囲の人に渡っていると感じます。
| TEL | 024-943-2380 |
|---|---|
| 屋号 | 株式会社 宝来屋本店 |
| URL | WEBサイト:https://www.e-horaiya.com/ |
| 住所 | 〒963−0725 福島県郡山市田村町金屋字川久保54−2 |